2026年は60歳。勤務38年(端数月切り上げです)で、定年を迎えます。
リタイアメントプランニング(=退職後や老後の生活設計)と老後生活資金(=退職金、年金、貯蓄、年金以外の老後収入 など)について、真剣に取り組まなければならない時期に、なってしまいました。
そこで、退職金について勉強してみました。
退職金+DC年金は、私の場合は、一括で受け取とった方がよいか、それとも年金で受け取った方がよいか。で、悩みました。手元に残るお金を少しでも多くしたい。という方針で
シミュレーションしました。
結論は、一括でうけとる方針としました。
退職金、一括受け取りに決めた理由と税金の話
退職所得控除の仕組み
退職金は、長年の勤労に対する功労金であり、今後の生活を支える大切な資金です。そのため、税金面で優遇されており、その中心となるのが退職所得控除です。これは、退職金から一定額を差し引いて、課税対象となる金額を減らす制度です。国税庁のページによると、勤続年数によって控除額が変わります。
- 勤続年数20年以下: 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
- 勤続年数20年超: 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
私の勤続年数は38年ですので、退職所得控除額は以下のようになります。
800万円+70万円×(38年ー20年)= 2,060万円
つまり、2,060万円までは退職金に税金がかかりません。この控除額の大きさこそ、退職金の一括受け取りが有利となる最大の理由です。
退職所得控除額を超えた場合の税金計算
もし退職金が控除額を超えた場合でも、税金の計算方法は、さらに優遇されています。退職金の収入から退職所得控除額を引いた金額の半分が、課税対象となります。
退職所得=(退職金の収入金額−退職所得控除額)×1/2
この計算で算出された金額に対し、所得税と住民税が課税されますが、他の所得(給与所得など)とは分離して計算されるため、税率が上がる心配がありません。
退職金を一括で受け取った後も、DC年金の資産を運用し続けようと考えています。
拠出はできませんが、少しでも資産が増えればいいなと思っています。
今後のリタイアメントプランニングが少しずつ具体的になってきました。
今後の計画や実際の体験談も、ブログで紹介します。
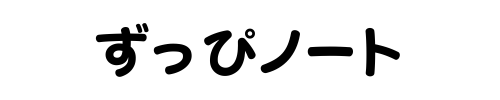

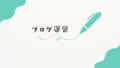
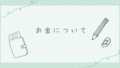
コメント